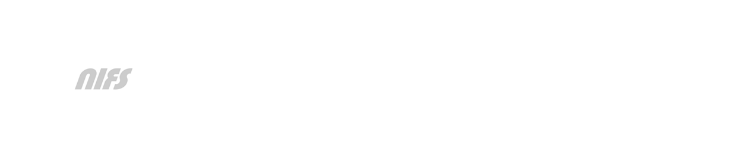研究目的
核融合炉がもつ固有の安全性を鑑みると、安全研究の対象は核融合反応に起因する放射線、燃料であるトリチウム、中性子によって生成される放射化物(放射性物質)に集約されることがわかります。核融合炉施設周辺を対象とした安全性研究では、放射線による公衆の被ばく低減や、自然環境における放射性物質挙動研究と生物に対する影響の科学的な理解が求めらています。核融合炉に関連する放射性物質の中でも移動性の高いトリチウムが地球環境へ放出されると、気圏・水圏・土壌圏での物理化学過程を通じてトリチウムが水の化学形態へと移行し、水を介して直接的、間接的に動植物(生物圏)に取り込まれる。トリチウムは水素同位体であるため、光合成を介して水(組織自由水中トリチウム: TFWT)から有機物(有機結合型トリチウム: OBT)に取り込まれ、また水や有機物として生命の根幹である細胞に到達します。トリチウムから放出されるβ線のエネルギーは低く飛程が短いため、細胞内での局所的な影響に関する知見が求められています。
日本の核融合原型炉開発を担う六ヶ所村の核融合施設では、施設の拡充に伴いトリチウムの使用が想定されます。このことから、六ヶ所村および周辺の下北半島を対象として環境トリチウム濃度を調査すること、そして環境放出を想定した低濃度トリチウムおよび低線量・低線量率放射線の生物影響研究と協働することで、今後の核融合トリチウム安全評価に資する科学データの取得を目的としています。