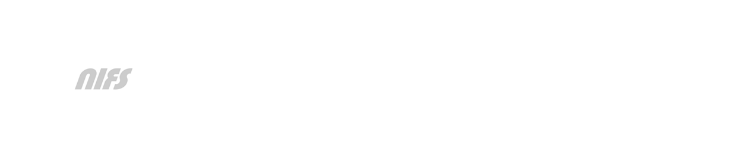研究計画
六ケ所および周辺の下北半島における環境トリチウム観測
エネルギー関連施設が集積する青森県六ヶ所村では、量子科学技術研究開発機構(QST)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所を中心に核融合工学に関する様々な研究が進められており、今後大量トリチウム取り扱い施設の整備が計画されている。核融合発電の社会実装には、放射性物質であるトリチウムに対する安全・安心の醸成は重要である。環境中のトリチウムは主に水(HTO)として存在するが、施設がある六ケ所周辺の観測データは村内を中心とした地域に限られており、トリチウムによる施設影響の範囲を評価するため、下北地域から八戸地域までを幅広くカバーした調査が肝要である。本研究では、エネルギー関連施設が数多く立地する青森県六ヶ所村とその周辺地域において、環境水(河川・湖沼水、水道水等)を採取し、比較的高緯度地域における近年のトリチウム濃度レベルを把握し、地域住民のトリチウム理解の促進に寄与する。また、トリチウム測定用簡易大気水蒸気捕集装置の吸湿材から水分を効率よく回収するためのシステムを確立し、将来的な広域大気モニタリングのための基盤を構築する。
トリチウム生物影響に関する2つの研究課題
低濃度トリチウム生物影響解析
環境レベルのトリチウム暴露をモデルとする生物影響の知見が不足している課題を解消するために、本研究では従来よりも環境レベルに近づけた低濃度トリチウムへの持続暴露による遺伝子および細胞への影響について解析する。遺伝子影響解析では、研究分担者の田内が独自に確立して線量率のしきい値を見出した突然変異高感度検出系を、あらたに改良した実験系を用いる。さらに高感度に突然変異を検出できる実験系を用いて、低い放射線量において放射線型の遺伝子変異が見られるかを解析する。また、トリチウム水で見つかった線量率のしきい値がトリチウムβ線特有の事象なのかどうかを確認するため、γ線を用いた比較実験にも取りかかる。細胞影響については、トリチウム処理濃度と細胞内取り込み量との相関および細胞内局在について、トリチウム水と有機結合型トリチウムのそれぞれについてデータを整備した上で、DNA二重鎖切断を検出する分子マーカーを用いた解析結果との関連性を検討する。
低濃度トリチウムをモデルとする低線量・低線量率放射線被ばく生物影響解析低濃度
低濃度トリチウムをモデルとする低線量・低線量率放射線被ばく生物影響について、先端的技術を用いて分子レベルおよび個体レベルで解析する。放射線発がんに着目し、分子レベルではその初期過程に関与することが想定される活性酸素によるミトコンドリアDNAの断片化がシグナルとなって慢性的な炎症反応を誘導することが関与するという仮説を検証し、細胞質に局在する有機結合型トリチウムの影響を解析する指標としての可能性を検討する。個体レベルの解析では、放射線に高発がん性を示すモデルマウスを用いて、低線量および低線量率放射線による発がんリスクやそのメカニズムを解析する。
期待される成果
六ヶ所村の核融合施設は、今後、大量のトリチウムを使用する研究が計画されている。また、トリチウムが放出される六ヶ所核燃料再処理工場の稼働も見据え、それらの影響を正しく評価するために、事前の環境トリチウム観測が求められる。一方、福島第一原子力発電所の処理水海洋放出や核融合科学研究所の重水素実験の例を挙げるまでもなく、僅かなトリチウム放出でさえ、その環境挙動や生物影響に関する情報が不十分であると公衆から大きな反発を招く。本研究を実施することで、比較的高緯度に位置する六ヶ所関連施設周辺の環境トリチウムデータを取得し、施設影響評価ための環境データベースとして活用できる。また、トリチウムの生物影響に関する研究は、科学的根拠、データを基にしたパブリックコミュニケーション(リスクコミュニケーション)へと繋がり、公衆に対する安全・安心の醸成が期待できる。